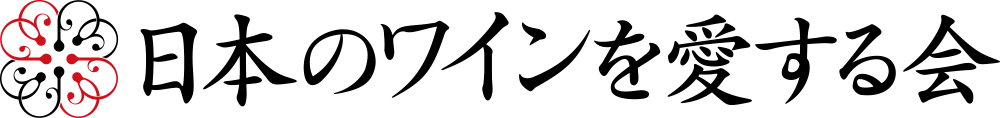2025年5月のゲストは山形県南陽市、「酒井ワイナリー」の代表取締役、酒井一平さんです。
今回は自慢のカベルネ・ソーヴィニョンの赤ワイン「灰鷹」で乾杯!大学卒業後はすぐに帰郷した一平さん。今では信じられませんがご本人曰く、当時のワイナリーはボロボロで・・・。(全5回 3回目)
辰巳:5月のお客様は、明治25年創業のワイナリー、山形県「酒井ワイナリー」の5代目当主、酒井一平さんです。
本日も「エネコ東京」で収録しております。プリオホールディングス総料理長の井村貢シェフです。
全員:よろしくお願いします!!!
辰巳:今日はちょっと色が薄め?の赤ワインです。ボルドーはクラレットって言って元々こんな色だったそうですけどね、最近こういう色がまた出てきて、僕は嬉しく思っています。では乾杯しましょう!
全員:カンパ〜イ🎶

【灰鷹(ハイタカ)2022】
http://www.sakai-winery.jp/wine3/05_haitaka.htm
井村:見た目はすごく透明感があるんですが、それに反して味はしっかり。
辰巳:そうですね。渋みというかけっこうタンニン感がある。
井村:輪郭がしっかりしてるワインという印象です。
辰巳:キリっと’人に媚びないタイプ’のワインですね笑。こちらはどういうワインですか?
酒井:「灰鷹」というカベルネ・ソーヴィニョン100%のワインです。ヴィンテージは2022、樽で1年間熟成させたものです。
辰巳:最近は鳥のラベルが増えてきてるみたいですが何種類ぐらいあるんですか?
酒井:今は造れなくなったものを含めれば10種類ぐらい。
辰巳:僕は尉鶲(ジョウビタキ)が好きで、まだ日本にオレンジワインが少なかった頃のスパークリングで、当時飲んで「美味しいなー!」と思った記憶があります。
酒井:ありがとうございます!
辰巳:最初の頃は泡が吹きこぼれてなかなか止まんなかった笑。
酒井:苦笑😅
辰巳:ほかにはどんなのがありましたっけ?
酒井:「四十雀(シジュウカラ)」っていうオレンジワインや「緑啄木鳥(アオゲラ)」「翡翠(カワセミ)」。農家さんの都合で今は造れなくなってしまったメルローの「鵟(ノスリ)」・・・。
辰巳:みんな赤湯の地元の鳥なんですか?
酒井:そうですね。ブドウ畑に現れる鳥たちの名前、です。一応赤ワインは猛禽類、雑食だったり草食だったりする小鳥たちは白ワイン、という付け方になってます。
辰巳:なるほど〜。その中でも灰鷹は猛禽類でも大きな方?
酒井:ノスリとかに比べればちょっと小ぶりですが、それでも灰鷹っていう名前だけあって”精悍な猛禽類”って感じですね。
ちょっと色が薄くて線は細いんですけど、しっかりと赤ワインとして主張できるワインかなぁと思ってこの名前をつけました。
辰巳:だんだん色が出にくくなってきたってこともあるんですか?
酒井:こちらに関しては、(先週の)シャルドネを作ってくださってる寒河江の契約農家さんなんですが、盆地の平らなところで作ってるブドウなんです。だから最近の温暖化の影響で、「高温で色がつかない」現象が起きていて。
昔はもっと色が濃かったんですけど、今はロゼワインのような色合いになってしまってる。。。
辰巳:でもあえてロゼにしようとはせずにこのスタイルで?
酒井:実際ロゼワインを造ったことはあんまりなくて。重要なのは「そのブドウを100%引き出してあげること」。
だから”薄いからロゼワイン”ではなく、「薄いなら薄いなりの赤ワインを造った方がいいのではないか?」という考えで造りました。
これに関しても色は薄いですが醸しを3ヶ月以上してるので、しっかりとしたタンニンが出てきました。
辰巳:ネッビオーロみたいな強いタンニン感がある。さ、こちらに合わせたお料理はなんでしょう?
井村:今日は牛頬肉を使ったリゾットです。ワインをテイスティングしてみて「リゾットは面白いかも」と、コショウと最後にバターをひと片だけのシンプルなお料理にしました。

【牛頬肉のリゾット】
酒井:旨みもすごく強く出ていてすごく美味しい♡うちのワインも澱からも旨味を抽出しようと思ってますので。
『旨みのあるワイン』を目指してる我々にとっては、こういった強い旨みのあるお料理だと非常に合わせやすいのかなと思っています。
辰巳:なるほど。方向性としては何か手を加えたりだとかは?この樽は?
酒井:先週のシャルドネと同じくこれも古樽100%。新樽はどうしても香りが強くつきすぎてしまうので、こういう線の細いワインだと、樽の香りがメインになりかねない。
後味に長く残る滑らかなタンニンとか澱からくる旨みだとかがマスキングされてしまいがちなので。。。
古い樽を大事に使って、ブドウとワインの個性を出していけたら、と思ってます。

辰巳:赤ワインと白ワイン、どっちの方を多く造ってますか?
酒井:10年前ぐらいからデラウェアの生産が非常に多くなったので、そういう意味でも白が6割ぐらいですかね。あとはマスカット・ベーリーAとかの赤ワインが4割。ロゼワインは造ってません。
辰巳:ワイナリーが始まって約130年。ブドウ品種は最初は何から始めた?とか記録が残ってたりするんですか?
酒井:最初はそれこそいろんな品種が導入されたらしいんで、今ではぜんぜん作られてないような品種。当時の人が書いてる記録なんでよくわかんないんですけど”ベーコン”、とかいう品種だったりとか笑。ぁ、シャスラーも育てられてたみたい、それも天皇陛下に献上されたことがあるみたい、な。すごく良質なブドウが育てられたりしてたみたいなんですが、アメリカからベトとかの病気がやってきてからは壊滅状態。
それに耐性のある品種が生き残ったって感じみたいです。それがデラウェアだったりマスカット・ベーリーAだったりで現在まで。
でもいちばん古いブドウは江戸時代から植えられている甲州。
辰巳:甲州のワインも造ってるんでしたっけ?
酒井:はい。赤湯でも江戸時代から作ってたんですけど今はもうほとんど作ってない。それでも収穫時期が遅い品種ですし、今は生食用の需要はほぼなくなりましたから。
辰巳:同じ山形でもね、鶴岡の方はすばらしい甲州作ってますけど赤湯でも甲州作ってたんですね。
ぁ、そうそう、これ聞こうと思ってたんですけど。戦時中デラウェア(敵国語だから)のことを”小姫”と呼んでたらしいですが甲州のことは?
酒井:”甲州は甲州”、特殊な名前では呼ばれてなかったみたいです。
辰巳:では先にリクエスト曲を聴いて後ほどまたお話を伺います。今日はなんにしますか?
酒井:じゃぁ、また、くるりの「東京」でお願いします。
辰巳:(外野に向かって)知ってますか?
外野:???
辰巳:くるりってどこ出身ですか?
酒井:京都です。
辰巳:💦💦優香団は知ってるんですけど・・・。
ではくるりんではなく、くるりの「東京」です。

くるり「東京」(1998年)
https://www.youtube.com/watch?v=9osrk5jXCUY&list=RD9osrk5jXCUY&start_radio=1
辰巳:ま、東京に出てきて、6年間勉強して、そのまままっすぐ地元に戻ったんですか?
酒井;はい。
辰巳:それが2004年という。ほんとに『日本ワイン』という言葉も含めた運動を、山本(博)先生を始めとした有志が始めた頃なんですよ。
その頃から僕も応援し始めて『日本ワイン』がダァァァっと広まったという時代です。もう20年も経ってるのが驚きですけど。
(大学卒業して)東京から戻ってきた時はどうだったんですか?だってその時はお父さんが(ワイナリー)やってたんでしょ?どういう親子関係だったんですか?
酒井:ぶっちゃけて言えばもううちの親父はやる気がなかったんで笑笑。売れない時代が長くてずっとやさぐれてるって感じですね笑。
かなり不遇の時代でしたから。帰ってきた時には(実家の)かなりのアラが目立って、、、。2004年に帰ってきた年の醸造の終わりの段階で、「あとは自分がやります」と言ったんです。
その段階で、親世代との葛藤がいろいろあるんじゃないかと思うんですけど、うちは「じゃぁ思えが全部やれ!」っと。だから帰ってきてから2年目で全部自分がやることになりました。
辰巳:2005年から?
酒井:そうです。そこから1人でやることになりましたし、一族の畑は戦前はものすごくあったのに、農地開放でほぼすべて持ってかれてしまったもんですから、残ったところを大叔父がやってて、でもそこももう耕すことができないからと買わせてもらいました。
だから自社畑をスタートさせたのも2005年からでした。
辰巳:そうでしたか。でもそっから急にぐわぁぁっと「山形に酒井ワイナリーあり」を知らしめた。
その翌年かな、ちょっと早めに取材しないと、で「葡萄酒浪漫」で取材に行きましたね。
酒井:その節はありがとうございました。一族のやってた畑と、契約農家さんのやってたカベルネ・ソーヴィニョンがあったのはすごく幸運だったなと思います。
カベルネ・ソーヴィニョンに関しては、日本で1、2を争うぐらいのクオリティのブドウが採れてたので。
そう言った意味で、「ワイン造りとはナンゾヤ?」と思って半信半疑ながら実家に帰ってきたんですけど、そのブドウのワインを飲んでみて「これはイケるぞ💡」という手応えを持てたのはすごく心強く、「赤湯というブドウの銘産地を信じられたこと」が自分にとっては自信になりました。
辰巳:故郷が温かく出迎えてくれた、って感じなんですかねぇ。
酒井:昔の先輩たちが残してくれた遺産が今の自分を生かしてくれてるという感謝の念を抱いたことを強く覚えています。
辰巳:それで「ワイン造り面白い!」と?
酒井:そうですね。実際2004年に初めて造った時は培養(乾燥)酵母、亜硫酸もしっかりと使ったんですけど、非常にポテンシャルの高いワインが出来た、
辰巳:戸塚メソッド?
酒井:はい、あの時の味は今でも忘れられない。
辰巳:いいワインが出来たってことでしょ?
酒井:非常に良かったです。その年(2004年)がすごい良かったのと、当時は最高気温が30度を超えるか超えないかっていう気候だったので、非常に伸びやかな酸となめらかなタンニン。
カベルネ・ソーヴィニョンとしても長期熟成可能な信じられる品質だったんで、すごく幸せな時代を生きられたなと思いました。
辰巳:やっぱり’タイミング’も合ったんでしょうね。
酒井:人との出会いとか地元のブドウとの出会いとか、そういったものの積み重ねでしょうね。それがもしなかったらすぐに辞めてたかもしれない、潰れてたかもしれない。当時ワイナリーとしてはほんとボロボロでしたから。
辰巳:それは天が、神が、彼に絶対ワインを造らせるべきだと判断したんじゃないですか?笑。
酒井:はは、まぁそう思ってくれるんであれば死力を尽くしてこの生産地を残さなきゃいけないなぁというふうには思いますね。
辰巳:イメージ的には”ワインに没頭している若き哲学者”だったんですよ。そっからは脇目も振らずに?
酒井:今は脇目振り始めてますね笑。言ってしまえば、ブドウ栽培してワインを造るっていう農業をやっている中で「この地で農業をする意味は何か?」を考えた時に、その土地で生き続けるということは、ブドウだけじゃなくて、さまざまな農業もやるべきなんだろうし、”いろんな生き物がいてブドウが生きる”。っという考えから2007年から畑の中に羊を放牧し始めました。
辰巳:そんなに早くから?そうなんですよ〜、羊いっぱいいるんです〜🐏。
酒井:おととし3頭食べてしまって(😭)今は11頭。その羊とか、畑の中にもいろんな生き物がいて、「いや、いるべきだ、目指すのは森だ」と。
辰巳:そうですか。ミツバチも飼い始めて蜂蜜作ったりといろんな意味で面白い。この続きはまた来週ということで。
全員:ありがとうございました!!!


News Data
- プリオホールディングスpresents 「辰巳琢郎の日本ワインde乾杯!」
2025年5月15日放送回
- ワイナリー
有限会社酒井ワイナリー
http://www.sakai-winery.jp- 収録会場
エネコ東京
https://eneko.tokyo/