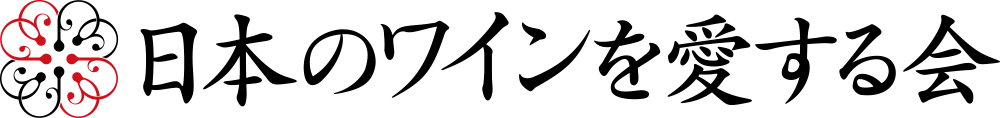2025年5月のゲストは山形県南陽市、「酒井ワイナリー」の代表取締役、酒井一平さんです。
今回は赤湯の銘醸地の一つ「名子山」で乾杯!ワイン愛、赤湯愛溢れる話題満載の最終回です!
(全5回 5回目)
辰巳:5月も最後の週になってしまいました。ゲストは東北最古のワイナリー、山形県南陽市「酒井ワイナリー」の5代目、酒井一平さんです。そしてプリオホールディングス総料理長、井村貢シェフです。
全員:よろしくお願いします!!!
辰巳:今月は5回ありますが、乾杯のワインが白・白・赤・赤・赤というのはこれまでではめずらしいですね。泡だったり、間にオレンジだったりロゼだったりするんですけど、赤の3連発というのはなかなかなかったかも笑。では乾杯したいと思います。
全員:カンパ〜イ🎶

【名子山(なごやま) 2016】
http://www.sakai-winery.jp/wine3/01_nagoyama.htm(こちらのヴィンテージは2019です)
井村:前週もそうでしたけど、クリアなのに味わいがグーっときますね。迫ってくるような旨みがあります。
辰巳:本当に旨みがあります。このワインは?
酒井:自社の名子山という畑で造りました、2016年の赤ワインです。
辰巳:名子山はカベルネ・ソーヴィニョン主体でしたっけ?
酒井:そうです。そこにメルローが2割程度、あとはほんの少しのカベルネ・フランとかですね。
辰巳:ではまず、ここのワインに合わせたお料理をいただきましょう。
井村:今日は、シンプルにローストチキンにしました。
辰巳:丸焼き?🦃
井村:”野菜もチキンも全部放り込んで焼く”本来の作り方で。ソースは舞茸、しめじ、エリンギ、マッシュルーム、、、
キノコをたくさん使ってあります。「このワインの旨みに合わせるには絶対こういう料理が食べたくなるなー」で作ってみました。
全員:いただきます🍴🍴🍴

【若鶏とじゃが芋のローストチキン ローズマリー風味 キノコのソース】
辰巳:そういえば一平さん、好き嫌いはないんですか?
酒井:特には。納豆が苦手以外には大体食べられます。
辰巳:うん、思ったよりシンプル。酒井ワイナリーのワインもそうですけど日本のワイン全体が”自分が自分が”って前に出てこないワインが多いので、料理には合わせやすいですよね。
井村:ほんとに。ありがたいです。
酒井:うちのワインもしっかりと旨味を出していこう、長期熟成可能にしようと考えてますし、このキノコと鶏肉の旨みが非常に合ってて嬉しく思います。ありがとうございます。
辰巳:名子山ってどのあたりでしたっけ?
酒井:赤湯っていう町の坂の道の名前なんですけど、この辺りのブドウの生産地の一帯を「鳥上坂(とりあげざか)」と言っているんです。
辰巳:だから「Bird Up(バーダップ)」。
酒井:笑。このエリアには3つの山があって、その一つが「名子山」。もう一つは、ここにも自社畑があるんですけど「十部一山(じゅうぶいちやま)」。関所を通る時に税金1/10取られたーみたいな謂れが。そこは名子山の東っ側にあります。その西っ側にあるのが「大沢山」。その3つの山が、赤湯の「鳥上坂」と言われているブドウのメイン産地なんです。
辰巳:前に取材に行った時にビックリしたのは”垣根の畑で雑草とかまったく刈らないんで、それらがどんどん成長して、『いずれはこれらがブドウの樹に巻き付いて・・・「これが自然の姿じゃ?🧐」』、の話はあまりにもショッキングな話だったんですけど。あれはナニ山だったんでしたっけ?
酒井:笑。あれが「名子山」。
辰巳:傾斜は激しいし鬱蒼とした「よく見たら森の中にブドウが」みたいな所だったんですよ。今どうなってるんですか?
酒井:もうその当時から温暖化が進んでいたのと、それと共にバンプ(病)も進んでしまっていて、そっちもどうにもならない。
っというような状況になってます。
辰巳:あそこもカベルネ・ソーヴィニョンでしたっけ?
酒井:あとはメルローとか、、、。
辰巳:そこにヤマブドウ系を入れたらいいのにー、っと当時言ったか言わなかったかは覚えてないんですが。。。
酒井:だから耐病性のある品種は入れなきゃいけないとは思ってるんですけど。*JVA という組織があって、海外から耐病性のある品種とか、苗木はどんどん取り入れてるんですけど、4月の20日(←収録は4月7日でした)にシンポジウムがあるので自分も温暖化について30分ぐらい話させてもらうことになってます。いずれにしても、病気にも暑さにも強い品種、
(*JVA:Japan Vinyard Association 一般社団法人日本ワインブドウ栽培協会)
辰巳:どんな状況にしても”色も酸も残る”品種ってことでしょ?そう、じゃぁ「なんでヤマブドウ系をやらないの?」、が、今日いちばん質問したかった。
酒井:何回かは試ったことはあります。でもクローンと、ほんとに山に自生しているのとはタイプがまったく違う。
だからそこらへんも含めて何回か造ってみたんですが、「デザインしないと造れない」。(←なんかカッコいい)
うちみたいな造り方だと”全てを絞り出そう!”。でもそれをヤマブドウでやろうとすると、”とんでもなくタンニンが強くてとても飲めないし10年経っても変わらない”っていうレベルのものになってしまって。
辰巳:でも最近は「ソフトプレス」とか”抽出弱め”が流行になってきたりしてますけど?
酒井:ですからヤマブドウに関しては、『高度の技術が必要である』。うちのスタイルで造るとするととんでもないことになってしまうので、今のところは躊躇してます。
辰巳:スタイルを変えたくないと?
酒井:そうです。今はかなり長い発酵時間取ってますんで、これをヤマブドウに適応するととんでもないことになる。
だから、もしかしたら自分じゃない誰か、別の醸造家にお願いしたら選択肢の中には残ってくるかなと。
辰巳:頑固なとこは頑固笑。
酒井:そうすね、”今までやり続けてきたことをやる”ってことでようやくワイナリーの個性だとか産地の個性が出来上がる。
今はまだまだ不十分。決定してなくて「これだっ!」ってことも言えてないことがあんまりよろしくないので、この先『これが赤湯のワイン文化だ』と言えるように(ガンバル)。
辰巳:赤湯にも新しく2つワイナリーができましたよね。イエローマジックとグレープリパブリック。
これで風景も変わるかなぁと楽しみにはしてるんですけど。コロナもあってこの2つのワイナリーもできて、何か影響はありましたか?
酒井:うちを含めた既存のワイナリーとは考え方も違うスタイルでしたし、いい刺激にはなってると思います。
ブドウに対する考え方とか、栽培の方法もちょっと違ってたりするんで。赤湯の畑だと、今まで水平上を段々畑にして栽培、がフツーだったんですけど、スキー場みたいに山を一面使って垣根栽培してるとこもある。
あとはデラウェア使って、新しいスタイルに挑戦するとか非常に新しいことが始まっている。だから昔に比べるとワインに幅が出たなと。
辰巳:話し込んでしまいましたが、ここで料理を食べながらリクエスト曲を。今日は何にしましょう?
酒井:・・・続いて、ナンですが💦、また、くるりの「愛の太陽」。これは最近の楽曲。
辰巳:これ知ってる人っ?
外野:しーん
辰巳:うちの若いのも知りませんよ。かなりマニアックなんじゃないですか?
酒井:ぇw、かなりメジャーなバンドではあるはずなんですけど💦音楽活動長く続けていて今だに新しい曲も出してますし、
「モノを作り続ける」ってことに対してはすごく共感性を覚える。
辰巳:京都のロックバンドでしたね。
酒井:ま、今は東京メインだと思いますが。

くるり「愛の太陽」(2023年)
https://www.youtube.com/watch?v=XxSsSKtQuqI&list=RDXxSsSKtQuqI&start_radio=1
辰巳:はい、今月は’くるり’が3曲も。ぜんぜん知らななかったんで勉強になりました。今も聴くんすか?
酒井:ですね。結局同じような音楽しか聴かない、のと、今だに続けてらっしゃるバンドの音楽を聴き続けてるって感じ。
辰巳:やっぱり5代目としては”継続は力”?
酒井:そうですね。やっぱり続けないことには見えてこないものはあると思います。
辰巳:確かにそれはそうです。6代目は?
酒井:今9歳です。小学4年生。
辰巳:今後継がいない大変な中で、
酒井:いやぁ、でも今は”子供だから継ぐ”ってわけでもないので、チャンスがあれば外の人に継いでもらうということも考えてます。
(←以前この番組で同じ山形のタケダワイナリー、岸平典子さんも同じことをおっしゃってました)
辰巳:ご自分が暗い(?)学生時代をすごしてプレッシャー受けたから?笑。(子供には)好きな道をと?
酒井:まぁそれもあります。得手不得手もあって。直系だからと無理やり継いだところで幸せになるわけでもないと思いますし、家族だけならまだしも従業員さんも契約農家さんもいる。
ワイナリーってかなり特殊な職業だと思っていて、能力がない人じゃないと今後さらに厳しいことになってくると思いますんで、まずは「能力のある人にワイナリーを注いでもらうのが一番いい」のかなと。
辰巳:今後さらに厳しい、っというのはどのあたり?
酒井:問題は2つ。”温暖化”と”少子高齢化”、ですね。温暖化については言うに及ばず、です。ブドウを育てづらくなってるんで、その分ブドウの品種、栽培方法、、、そういった防除体系も考えなきゃいけない。
でも今いちばんの問題は「それを実行する若い人がいない」。造る方もそうですし、飲み手も今後どんどん減っていくだろう、と。もう分かりきってることですけど。
「なんとかして’ワイン文化’を残していく、赤湯っていうワイン産地、微動産地を残していくにはどうしたらいいか?」をどうにかして考えていかなきゃいけない。そういう時代に今後どんどんなっていく・・・。
辰巳;それはそうかもしれませんね。

辰巳:あれ、奥さんは山形ワイン応援団で?
酒井:酒販店に勤めてて、自然派ワインが好きだっていうことでワインのイヴェントに応援しに来てくださってて、そこで出会った。
辰巳:山形出身?
酒井:香川出身で、でもその時は東京で仕事してたんです。その時に山形のイヴェントに手伝いに来ている時に・・・
辰巳:口説いたと?笑。
酒井:まぁ、そうすね💦
辰巳:ん、逆に口説かれたんですか?
酒井:いやま、口説いたんですけど笑笑。結局山形っていう片田舎に連れていくわけですから、そこら辺はあちらも大変だったんだろうなと。
辰巳:でも東京出身じゃなくて香川の人だったわけじゃないですか?太陽が燦々と輝く瀬戸内から笑、冬は暗くて寒い山形へ・・・。
酒井:そこら辺は葛藤があったみたいです。冬はすごい雪が降ってそれが嫌で出ていく人も多いのに、雪のないところからやってくるってのは、かなり勇気のいったことではないかと笑笑。
辰巳:最後のひと押しは?笑
酒井:「一緒にいいワイン産地にしましょうよ」。
辰巳:こういう口説き文句があちこちで出てくればいいですよね笑。ってそろそろ終わりですけど、こんなまとめ方でいいんすか?爆。
あと、日本も今ワイナリー増えてきて、まぁ乱立って言ったらアレなんですけど、こういう状況をどうご覧になってます?
酒井:いろんな形態のワイナリーさんも増えてますけど「でもなぜそこでワインを造らなければならないの?」「その意味は?」、、、をもっと突き詰めていかないと重要なところでつまづいてしまう。
始めたのはいいものの続けられないということになれば、その土地でのワイン文化ってのは途絶えるどころかその後も無くなってしまう。
「失敗した」という前例を作ってしまうとそこで出来るかもしれないワインの可能性を潰してしまう。だからワインっていうのは”農業そのもの”なので、ブドウ栽培を通してしっかり土地の特性を知ってもらって、それからワイン文化をしっかり育てて。っというふうに思います。
それがない限り、ワインは造り続けられるものじゃないと思ってます。短いながらワイン造って20年ちょっと、の人間が思うところです。
辰巳:いろいろ人の本読んだり勉強して自分を見つめる、哲学的だったりするんですけど、最近影響けてる人いますか?
酒井:最近読んだ本だとエーリッヒ(・フロム)の「愛するということ」という本ですね。『愛』とはどういうことかということをしっかりと口頭するという本だったんですけど。共感する部分、気付かされる部分があって。
ですからワイン産地、仕事してる畑を如何にして責任感を持って配慮、尊重して知識を得ることによって、行動することによって、ようやく愛せる・・・。「愛ある醸造家・栽培家・農家・生活者」としていられるか?っていうのがすごく重要だし、今後試されていく、っと思わされた本でした。
辰巳:それをもっと広げなくてはいけませんね。
酒井:そうですね、それを飲んで「おいしいな」と思ったら産地に来ていただき、もしかしてそこで暮らしたいってなれば。
ブドウだけじゃなく、米も野菜も羊もチーズもなんでもありますから、「ここで暮らしたいな」っていう誰かがいたらすごく嬉しいし、そこまでいかなくても「赤湯」っていう農産物を楽しんでいただけたらいいなと。
辰巳:赤湯、いいとこですよ。元々(湯に)赤い色がついてた?
酒井:戦で傷ついたひとが癒しに来て、血で赤く染まったっていう説もあって、
辰巳:その話も聞きました。みなさん、赤湯いいとこですんでぜひお出かけください!
5回に渡ってお伺いしました、5月のお客様は山形県最古のワイナリー5代目「酒井ワイナリー」酒井一平さんでした!
全員:ありがとうございました!!!


News Data
- プリオホールディングスpresents 「辰巳琢郎の日本ワインde乾杯!」
2025年5月29日放送回
- ワイナリー
有限会社酒井ワイナリー
http://www.sakai-winery.jp- 収録会場
エネコ東京
https://eneko.tokyo/